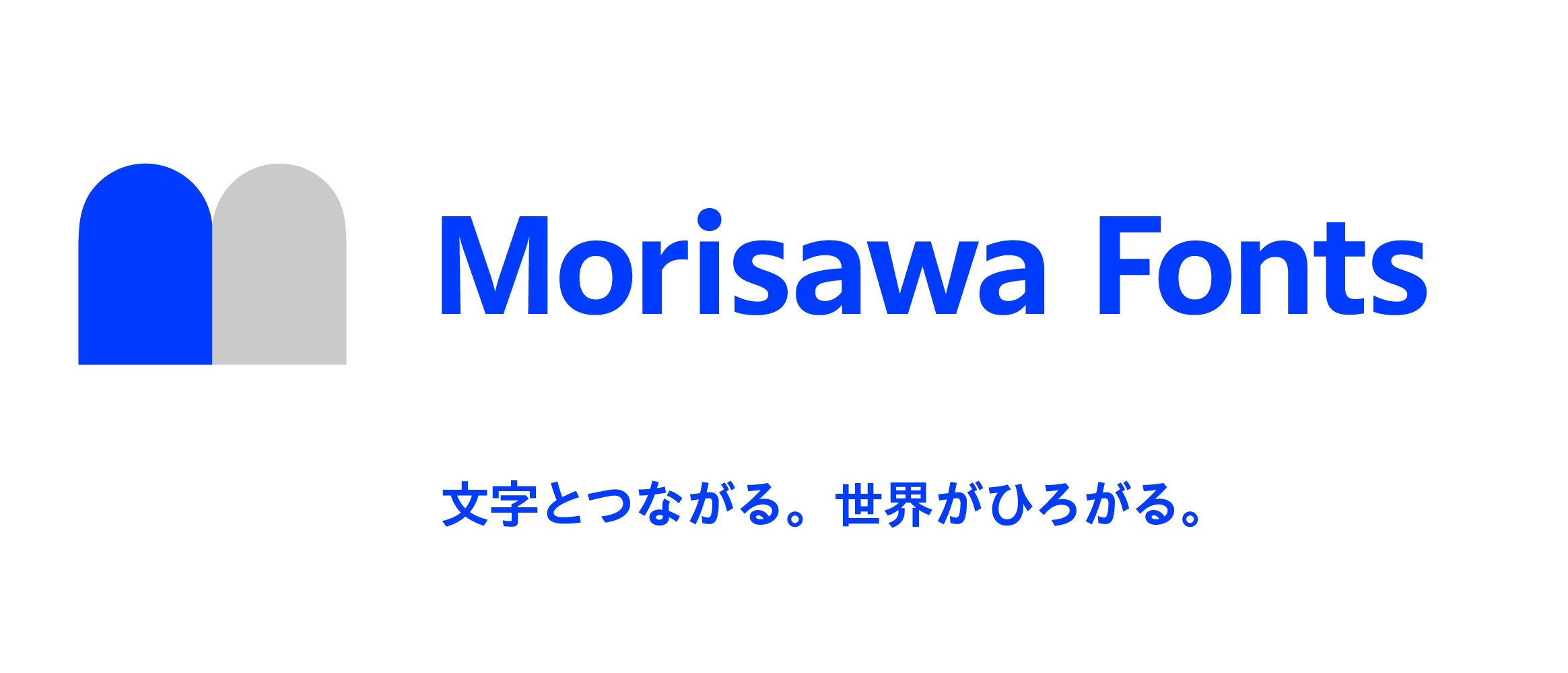【組版の基本ルール】引用符から○○向け書体までクイズ形式でご紹介!
カテゴリ:文字・組版

こんにちは、マツヲです。
もうすぐ2月も終わりということで、今の時期は「春の○○イベント」「○○スプリングフェア」など、イベント告知に関するチラシやポスターを目にする機会が多い気がします。
そもそも、日常生活を送るうえで「文字」は毎日のように見る機会がありますが、みなさま「組版の基本ルール」についてどのくらいご存知でしょうか?
今回はクイズ形式で「基本の組版&やりがちな『あるある組版』」をご紹介していきます!
組版について
冒頭で「組版」という表現をしましたが、もともとは活字を「組」み合わせて印刷用の「版」を作ること、現代においても、文字を並べてレイアウトを行うことを「組版」といいます。文字はそれ単体では意味をなしません。文章を作るためには、「文字や記号・数字を並べる=組版」をする必要があります。
「組版」は文字を自由に好き勝手に並べてOKな無法地帯ではなく、読みやすく文字を並べるためのルールがいくつか定められています(とはいえ、交通ルールのような絶対的なものではなく、あくまでも目安としてです)。
※詳しくは「JIS X 4051 日本語文書の組版方法」、または「日本語組版処理の要件(日本語版)」などをご参照ください。
ルールに沿って約物(句読点・つなぎ符・引用符など)の向きや使う順番、括弧(鍵括弧・山括弧など)の使い分けを行うことで、読みやすい文章表現になるということです!

デザインとして「あえて○○な向きで引用符を使う」「あえて○○な括弧を使う」などのケースもありますが、組版の基本ルールを知っておいて損はありません。
ということで、ここからはクイズ形式で組版の基本ルールをご紹介していきます。
※組版についてさらに詳しく知りたい方は「文字を組む方法」をご覧ください。
※日本語以外の言語に関する組版ルールは「MORISAWA PASSPORT 英中韓組版ルールブック(タイ語含む)」をご覧ください。
組版クイズ
全部で3問あります。
実際のポスターやチラシなどでもたまに見かける……かもしれない「あるある組版」ですが、あくまで基本ルールに適しているか否かを元にご紹介していきます。
①引用符:ダブルクォーテーション
【問題1】引用や強調したい箇所で使われることが多いダブルクォーテーションですが、AとBどちらが基本ルールに沿った使い方に当てはまるでしょうか?

正解は……「B」です。
AとBそれぞれで記号の向きが異なっておりますが、基本的に左側は「“」、右側は「”」を配置します。見た目がそれぞれ数字の「6」と「9」に似ているため、個人的には「数字が小さい方が先に来る」と覚えています……!
使用したい時は「かっこ」と入力して、変換候補一覧から左右セットの「“”」を探しだすと順番を間違えることはなさそうですね。
②引用符:ダブルミニュート
【問題2】引用や強調したい箇所には、ダブルミニュートが使用される場合もあります。今回は縦組みのサンプルをご用意しましたが、AとBどちらが基本ルールに沿った使い方に当てはまるでしょうか?

正解は……「A」です。
ダブルミニュートは別名「チョンチョン」と呼ばれることもあり、勾玉のような見た目のダブルクォーテーションと比較すると、すっきりとしたデザインですね。
ダブルクォーテーションは横組みで使用する記号であるため、縦組みの時はダブルミニュートをご活用ください。
 引用符サンプル
引用符サンプル
ちなみに、ダブルクォーテーションやダブルミニュートとは似て非なる記号「dumb quotes(別名:まぬけ引用符)」についてはご存知でしょうか?
こちらは記号自体の向きが垂直になっているのが特徴です。

まぬけ引用符はタイプライター由来の記号で、現在もコーディングでは使用されますが、組版として文章中に使用するものではありません。欧文を組版する場合も使わないよう、入力時はお気を付けください!

③用途別にデザインされた書体
今回のブログタイトル「組版ルール」から少しそれてはしまいますが、ここからは組版時に使用する書体についてご紹介していきます。
世の中にはさまざまなデザインの書体がありますが、事前に特定の利用シーンを想定してデザインされた「○○書体」があることをご存知でしょうか。
いわば「○○を組版するのに適した書体」のことで、「○○書体」はそれぞれ推奨している使い方があります。そこで今回は「新聞組版」に使用することを想定してデザインされた書体について、見ていきたいと思います!
【問題3】本文部分に新聞書体である「毎日新聞明朝」を使用した新聞のサンプルですが、AとBどちらが新聞組版として適した使い方と言えるでしょうか?

漢字は学習指導要領に掲載されている(学校で学習する)文字のみ手書き風にしているため、学校で習わない漢字は印刷の字形のままとなります。

つまり、同じ部首の漢字でも字形が異なる文字が混在するため、学習向け以外のコンテンツで使用することは、フォントメーカーとしてはあまりおすすめできなかったり……。
利用シーンに合わせて、使い分けていただければ幸いです!
いかがでしょうか?
組版ルールの基本を知っておくことで、自信をもって資料作成に挑めるかと思います!
子どもの頃は学校で作文用紙を使って文字の並べ方など組版ルールを学ぶ機会がありましたが、大人になるとなかなか学び直す時間が取れないですよね。
ということで、組版の世界をブログで発信していけないだろうか……と、本記事は不定期連載企画「組版(に関係するかもしれない)小噺」の第4回目となります。
前回の記事「マヤ文字の神秘」も非常に興味深い内容となっておりますので、今回の記事と併せてご覧ください。
また、モリサワではこのような組版の基礎知識や書体ごとの特徴、デジタルフォントの扱い方をまとめて学べる講座「文字組版の教室」を通年開催しています。
次回の講座日程は暖かくなる頃かと思いますが、モリサワ公式SNS・ホームページや以下のメルマガ「DTP Lab. Information」にて情報配信予定ですので、ぜひフォロー・ご登録をお願いします!
次回以降も、不定期で組版の世界を覗ける記事を企画しています。
お楽しみに♪
DTP Lab. information メールマガジンのご案内
本ブログの更新や、イベント・セミナー情報などをメールマガジンで配信しています。
今後の情報配信をご希望の方は、ぜひ下記よりご登録ください。
DTP Lab. information メールマガジン登録フォーム
■おすすめ関連記事一覧
文字・組版
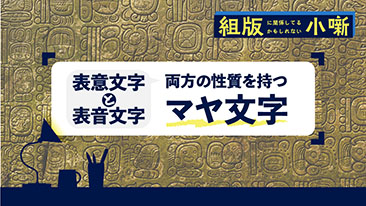 |
マヤ文字の神秘
2023年01月11日 |
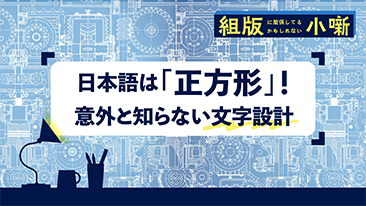 |
日本語は「正方形」! 意外と知らない文字設計
2022年09月08日 |
 |
どうして「10.5pt」?文字に関する単位のヒミツ
2022年08月17日 |