本田技研工業株式会社
コミュニケーション領域から
プロダクトまで
「Hondaらしさ」を発信する
コーポレートフォントを開発

-
本田技研工業株式会社
アシスタントチーフエンジニア
経営企画統括部 ブランド・コミュニケーションセンター ブランドプランニングスタジオ大石 るみえ氏
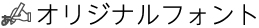
自動運転や電動化といった技術革新が進み、「100年に一度の大変革期」といわれているモビリティ業界。パラダイムシフトの渦中で、今後どのような価値を提供できるか各メーカーが問われている中、本田技研工業株式会社(以下「Honda」)は欧文と和文のコーポレートフォント「Honda Global Font」をモリサワと共同開発した。制作のねらいや、コーポレートフォントに込めたこだわりについて、担当の大石氏に伺った。

コーポレートフォントを通じてグローバルに価値を発信
2023年、Hondaはグローバルブランドスローガン「The Power of Dreams」を再定義し、「How we move you.」という副文を加えた。これを機に、未来のHondaのあるべき姿や方向性を国内外に広く発信するため、グローバルブランドアセットの強化を図ることになった。具体的には、多岐にわたる各事業の個性を活かしながらも、通底する「Hondaらしさ」をひとつの世界観として発信するための取り組みである。
コーポレートフォント開発はその一環としてスタートした。フォントは「発信の一貫性をもたせるために非常に重要なツール」と、ブランドプランニングスタジオでコミュニケーションデザインを手がける大石氏は語る。「これまでは各事業が個別にフォントを選び、フォントに対する意識もさほど高くはありませんでした。なので、自社のオリジナルのフォントを作り使っていくことで、社員一人ひとりのブランドに対する意識を醸成する必要があると考えました」。

そして、従来よりHondaでは、プロダクトごとに独自のロゴやエンブレムが多数存在する。ロゴの魅力をより際立たせ、各事業の個性を明確に伝えていくためにも、文章や説明部分などに使用される汎用的なフォントはできるだけ統一し、Hondaの発信の土台とすることを目指していた。
入念なデザインコンセプトと、細部にこだわりクラフト感を持たせた欧文フォント
今回開発したコーポレートフォントはグローバル市場での使用を前提に、コーポレート部門などを中心とするコミュニケーション領域から、各事業のプロダクトで使用するフォントまで、共通して幅広く活用できることを要件とした。開発パートナーとしてモリサワを選んだのは、圧倒的なレスポンスの速さに加えて、対応力の高さが決め手だったと大石氏は振り返る。「(Hondaは)細かいところまでこだわる人が多い会社なので、表現したいことをすべて他社の方に汲み取ってもらえるかは未知数の部分もありました。ですが、モリサワさんは提案段階からタイプデザイナーの方が参加されてとても安心感があり、お互いにやりたいことを詰め込みながらいいものを作っていけると感じました」。
多言語への対応、長文での読みやすさという点から、欧文は「Clarimo UD PE」、和文は「あおとゴシック」をベースフォントに選択。その上で「機能性を土台に個性を表現する」というデザインコンセプトを設定した。「機能性」とは、自動車のメーターなどプロダクトで使用する上で不可欠な瞬間認知性、読みやすさ、識別性の3つを観点としている。そして「個性」は、他のフォントと混植しても違和感がなく、長く使い続けられる普遍性(Modern)と、“人中心”思想を基本とするHondaのモノづくり(Crafted)を反映している。
 設定されたデザインコンセプト
設定されたデザインコンセプト
実は、プロジェクトでもっとも時間をかけたのがこのコンセプトづくりだったという。「機能性の3つの観点を決める際はチームで議論を重ね、『モビリティに求められるフォントの機能性って何だろう?』という点から掘り下げました。モリサワさんにプロトタイプを作っていただきながら、並行してコンセプトを固めていったのです」。
これらのコンセプトに基づき、欧文は文字のカーブ部分がやや角張ったスタイルを採用。他に幾何学的なスタイルなども検討したが、内から力を発するようなフォルムが「人間味」を表現できると考えた。加えて、文字幅の狭いUIフォントを制作しても、ファミリーでデザインの印象を保つことができると判断し、現在のスタイルが選ばれた。

そして、スタイルの核としてアルファベットの「O(オー)」をピックアップし、開発のはじめにHonda側で理想の曲線形を検討、モリサワはそのフィードバックを受けて欧文フォントの骨格に反映させた。文字設計前の段階で、なぜそのようなプロセスを組み込んだのだろうか。
「文字のデザインはスタンス(骨格)、モーション(動き)、ディティール(末端)の3点を見ているのですが、基本となる骨格は一度決めたらすべての文字に反映されるという話をモリサワさんに伺い、最初にしっかり作り込んでおく必要があると考えました。加えて、プロダクトデザイン出身で曲線に強いこだわりを持つ人が自部門に多かったことも、理由のひとつです」。
自動車などをデザインする際は、曲線を美しく見せるため、鉄板を曲げ、ハリをつけるポイントに“溜め”の部分を作って調整するのだという。書体のプロであるモリサワチームも、ジャンルを越えたデザインの美意識に触れ大いに刺激を受けた。
メーターの主役となる数字は、特に「6」と「9」は多くのパターンを作成して検証を重ねた。ベースフォントである「Clarimo UD PE」のスタイルからは、巻き込むようなカーブ形状の「6」や「9」も考えられたが、ぼやけた状態での見え方なども考慮し、最終的にシャープな線を持つデザインに決定した。
また、混同しやすい「I(大文字のアイ)」と「l(小文字のエル)」を識別するため、小文字のエルは下部を右に曲げたデザインとした。他の文字にはない“ハネ”の要素は文章を組んだときに隣の文字との空間バランスが崩れやすく、読みづらさにつながる恐れがある。そのため邪魔にならない程度のハネの長さを考慮しながら作成している。

和文フォントは読みやすさと人間味のある印象を追求
開発は、和文と欧文フォントと並行して進める形で行なった。通常モリサワでは、欧文または和文のいずれかを先に手がけ、そのデザインに合わせてもう一方の書体を作る手順が多く、今回はそれに依らない珍しいケースであった。その中で、和文のひらがな・カタカナの開発には、欧文フォント以上に「機能性と個性をバランスよく盛り込む必要が出てきた」という。目指したのは「安定感がありつつ人間味のある印象」だったが、文章にしたときの読みやすさを重視すると「人間味」の部分が薄味になってしまうのだ。
「最初の(モリサワの)提案内容は要件を満たしているし、欧文の要素とも合っているのに、混植するとひらがなとカタカナが物足りなく見えてしまって。機能性を追求するほど無機質な印象になっていくので、手書きの要素を強く出す方向へ舵を切りました」

例えば、ひらがなの「あ」は、縦画の右端部分のカットを斜め上に調整した。これはストロークに準じると本来下がる部分ではあるのだが、あえて上げることで動きを出している。「や」も2画目の点の向きや書き方を変えたものを7パターン試作するなど、1字1字丁寧に提案と修正を重ねた。
加えて和文は、文章として組んだ際の文字全体のバランスにも留意する必要がある。ベースフォントである「あおとゴシック」は文字がやや小さく、長文で使用する際は問題ないが、短い文章や単語を表示する場合はまとまりに欠けて見える。そこで漢字をわずかに拡大し、それに合わせてかなも調整した。
また、通常フォントに加え、やや文字幅が狭いUIフォントも設計。UIフォントは社内文書を中心に使用する想定であるため、体裁が崩れないようにそれまでに使われていた既存のUIフォントと同幅としつつも、幅を狭めたことによって読みやすさ、美しさを損なわぬよう、デザインに微細な調整を施している。
「当社の資料作成は1ページの中に情報を詰め込むケースが多いのですが、それが『Honda Global Font』に置き換わったとき、ストレスを感じさせないことが非常に重要でした。「Honda Global Font」における和文のUIフォントの場合、幅が狭いのはひらがなとカタカナのみで、漢字は通常幅なので、違和感なく使えるようとてもバランスよく作っていただいたと感じています」。

コミュニケーションもプロダクトも、コーポレートフォントが普遍的な“Hondaらしさ”に
欧文と和文が完成した「Honda Global Font」は全社員と関係会社への配布を終え、日本国内での運用が始まっている。その反響を聞いた。
「大きなリアクションはありませんでしたが、それはつまり、多くの社員がスムーズに新しいフォントに移行できたということで、一番よい結果ではないかと思っています。ストレスを感じずに、日常的に使ってもらえていることの証ですから。プロジェクトメンバーが抱いていた“普遍的な存在になってほしい”という想いは、ひとまずクリアできたのではないでしょうか」
また一般的にフォント開発においては、タイプデザイナーをはじめとするプロジェクトメンバーが対面で何度もやり取りをする機会はそれほど多くない。しかしHondaは、最終判断の根拠を明確化することを非常に大切にしており、今回のプロジェクトでも定期的にメンバーが顔を合わせ、議論を交わす場を持った。共に画面を見ながら、その場で詰めの作業や検討が進められ、プロジェクトとしての一体感も高まった。「毎回お互いにほぼフルメンバーが集結して、いいものを作りたいという一心でディスカッションを重ねました。われわれもコーポレートフォントのデザインは初めてでしたので、とても新鮮な気持ちでモノづくりができました」と大石氏は微笑む。

今後はメーターやディスプレイ、物理スイッチなど、プロダクトへ広く展開していく予定だ。グラフィックや、デジタルデバイスで表示させるWebフォントとしての導入も始まった。Hondaの世界観を集約した「Homda Global Font」は、今後もさまざまな化学反応を起こしながらHondaのブランドイメージを支えていくだろう。































